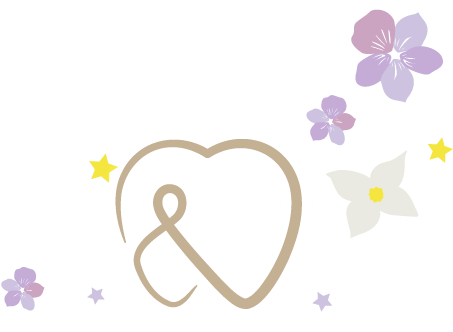こんにちは。兵庫県宝塚市「宝塚南口駅」より徒歩0分の宝南ショップス2階にある、宝塚南口駅の歯医者「宝塚歯科H&L」です。

矯正期間中は歯を移動させるために、1日20時間以上のマウスピースの装着が推奨されています。
しかし、長時間装置を装着するため、口臭が発生・悪化するケースがあります。そのため「矯正中に口臭が発生したらどうすればよいの?」と悩んでいる人も多く、口臭を発生させないためには何らかの対策が必要です。
今回は、マウスピース矯正中に発生する口臭の原因や口臭を放置するリスクについて、詳しく解説しています。併せて、自宅でできる口臭対策についてもまとめています。
目次
マウスピース矯正中に口臭が発生する原因

マウスピース矯正中は、マウスピースそのものや口腔内の細菌が原因となり、口臭が発生することがあります。ここでは、口臭の原因となる細菌が繁殖する理由について解説しています。
マウスピースの洗浄が不十分
マウスピース自体を清潔に保たないと、食べかすやプラークがマウスピースに付着し、細菌が繁殖しやすくなります。マウスピースはプラスチック製で、プラスチックにはニオイが移りやすいという特徴があり、毎日の洗浄が不十分だと口臭の発生につながります。
そのため、マウスピースを装着する際は、歯磨きとマウスピースの洗浄を欠かさないようにしましょう。
マウスピースの傷
マウスピースはやわらかい素材でできているので、丁寧に取り扱っていても傷つくことがあります。マウスピースに凸凹ができると、汚れが溜まってしまい洗浄してもきれいに取り除けません。
汚れが付着したマウスピースを長時間使用すると細菌が繁殖しやすい環境になり、ニオイを放つ原因となるでしょう。また、マウスピースのお手入れを行う際に研磨剤が含まれた歯磨き粉を使用すると、マウスピースを傷つける恐れがあります。
マウスピースを洗浄する際は流水下でやさしく擦る程度にし、洗浄剤を使用するときは専用のものを使用しましょう。
不十分な歯磨き
マウスピース矯正中に限らず、歯の汚れをしっかり落とすことは口臭予防に効果的です。ほかの矯正装置に比べて口腔ケアが行いやすいものの、患者さま自身の歯が汚れていれば口臭は発生します。
口臭や虫歯、歯周病を防ぐためにも、マウスピースを装着する前には歯磨きを徹底して行いましょう。特に、歯と歯の間のプラークは歯ブラシだけでは除去しにくいので、デンタルフロスや歯間ブラシなどを使用すると効果的です。
また、定期的に通院してプロのクリーニングを受け、口腔内の汚れを蓄積させないことも大切です。
唾液の自浄作用が働いていない
唾液には自浄作用があり、食べかすなどの汚れを洗い流してくれます。
ただし、口呼吸などで口腔内が乾燥すると、唾液の自浄作用を十分に得られません。特に、矯正中は歯と唾液が装置で隔てられるため、通常よりも自浄作用が働きにくい状態といえるでしょう。磨き残しがあると汚れが蓄積し、口臭が発生する可能性も上昇します。
喫煙による悪影響
煙草に含まれているタールは独特のニオイを放つため、喫煙者がマウスピース矯正を行うと口臭の原因になります。タールは粘々していて歯や歯茎に付着しやすく、喫煙習慣がある人は非喫煙者に比べて口臭が強くなる傾向があります。
口の中が乾燥しやすい
マウスピースを装着していると、慣れるまでは口が閉じにくくなることがあります。口が閉じにくいと口腔内が乾燥しやすくなり、唾液の分泌も悪くなります。
唾液には自浄作用や抗菌作用があるため、乾燥が原因で唾液の働きが悪くなると、口腔内がネバつき口臭も発生しやすくなります。
歯茎の炎症
歯磨きが不十分でプラークが蓄積すると、歯茎に腫れが生じることがあります。歯周病菌による細菌感染が腫れの原因です。歯周病菌は口腔内のたんぱく質成分をもとに、口臭の原因成分である揮発性硫黄化合物を作り出します。
そのため、歯茎の炎症がひどくなり歯周病になると、ガスが発生し口臭がきつくなる可能性が高いです。口臭を予防するためには、口内やマウスピースのお手入れ同様に歯茎のケアも欠かせません。
マウスピース矯正中の口臭を放置するリスク

細菌の繁殖が口臭の原因ですが、放置すると不快なニオイだけでなくさまざまなリスクを伴います。以下では、矯正中の口臭を放置するリスクについてまとめています。
治療が計画通りに進まない
細菌が繁殖して、虫歯や歯周病に罹患すると、計画通りに矯正治療を進められない可能性があります。矯正治療を中断して治療を優先するため、治療期間の見直しも検討しなければならないでしょう。
虫歯や歯周病になるリスクが高くなる
汚れが付着したマウスピースを装着していると細菌が繁殖して、虫歯や歯周病になるリスクが高くなります。トラブルを避けるためにも、歯磨きとマウスピースの洗浄を丁寧に行い、細菌の繁殖を抑えるように気をつけましょう。
口内炎などの炎症を発症する
口臭を放置すると、細菌が増殖して口内炎やウィルス性疾患になるリスクが高くなります。口内炎の中で最も多くみられるのが、アフタ性口内炎です。
免疫力が低下しているときに細菌感染を起こし、口腔内や口唇、舌の粘膜、歯茎などに発症します。口内炎が悪化すると、痛みでマウスピースの装着が困難になり、矯正治療の遅延につながるケースもあります。
自宅でできるマウスピース矯正中の口臭対策

口臭が気になったら、以下の方法で口臭対策を行いましょう。
マウスピースの適切なお手入れ
誤った方法でお手入れをすると細菌が繁殖して口臭の原因になるため、口臭予防にはマウスピースの適切なお手入れが欠かせません。マウスピースの素材のプラスチックは熱に弱く熱湯を使用すると変形する恐れがあります。
また、強い力でゴシゴシ磨くと、マウスピースが傷つくため、指で擦って取れない汚れがある場合は、毛のやわらかい歯ブラシでやさしく擦りましょう。歯磨き粉に含まれる研磨剤でもマウスピースが傷つくので、歯磨き粉は使わないで水かぬるま湯で洗浄してください。
週に1回程度、マウスピース専用の洗浄剤を使用するのも効果的です。定期的に使用すると、目に見えない汚れや口臭を除去できます。
ただし、使用頻度や使用方法は製品によって異なるため、説明書をよく読んで使用してください。
マウスピースを正しく保管する
マウスピースを洗浄した後装着しない場合は、水分をしっかり拭き取り、タオルの上などに置いて乾燥させてから専用のケースに入れて保管しましょう。濡れたままの状態やしっかり乾燥していない状態でケースに入れると、細菌の繁殖やカビが発生する可能性が高いです。
また、直射日光が当たる場所などに保管しているとマウスピースが変形する恐れがあり、ティッシュなどに包むと誤って紛失する恐れがあります。
唾液の分泌を促す
口臭予防には、唾液の量を増やすように意識することも効果的です。唾液の量を増やすためには、以下の方法が有効です。
- 食べ物をよく噛む
- 水分を多く摂る
- 鼻呼吸を意識する
- 唾液腺を刺激する
唾液腺マッサージを行うのも、唾液の分泌を促すのに有効な方法のひとつです。唾液腺には耳下腺・顎下腺・舌下腺の3種類があります。それぞれの唾液腺を親指で軽く円を描くようにもみほぐすと唾液が出やすくなります。
また、通常よりも多く水分を摂取したり鼻呼吸を意識して行うと、口腔内の乾燥対策に有効です。水分を補給するときは、虫歯の原因になる糖分を含まないものを選びましょう。
まとめ

マウスピース矯正中は、お口の中の乾燥やお手入れ不足などが原因で口臭が発生しやすくなります。細菌が繁殖しやすい環境になると、口臭はもちろん様々な口腔内のトラブルも引き起こします。
矯正中の口臭は正しいお手入れと口腔ケアで対策可能です。マウスピースに付着した汚れはこまめに落とすように心がけ、口腔内も清潔に保つようにしましょう。
ただし、口臭が強くなってきたら歯周病が重症化している可能性が高いので、早めに歯科医院を受診しましょう。
マウスピース矯正を検討されている方は、兵庫県宝塚市「宝塚南口駅」より徒歩0分の宝南ショップス2階にある、宝塚南口駅の歯医者「宝塚歯科H&L」にお気軽にご相談ください。