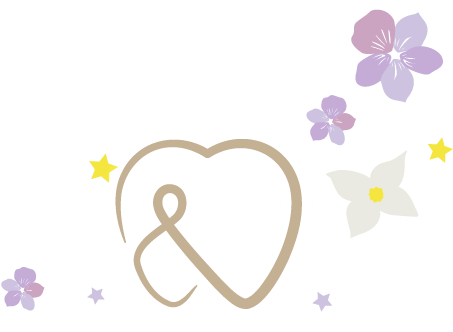こんにちは。兵庫県宝塚市「宝塚南口駅」より徒歩0分の宝南ショップス2階にある、宝塚南口駅の歯医者「宝塚歯科H&L」です。

お子さまの歯と歯の間に隙間があっても「永久歯が生えそろえば治るのでは?」と考える方も多いかもしれません。成長とともに治るだろうと放置していると、将来的に噛み合わせや発音に影響を及ぼす場合もあります。
この記事では、子どものすきっ歯の原因や放置するリスク、治療方法について詳しく解説します。
目次
すきっ歯とは

すきっ歯とは、歯と歯の間にすき間がある歯並びのことです。歯科では空隙歯列(くうげきしれつ)と呼ばれ、なかでも前歯の中央にすき間ができた状態を、正中離開(せいちゅうりかい)と呼びます。
成長の過程で一時的に現れる場合もありますが、隙間が閉じずに空いたままになるケースも存在します。
子どもがすきっ歯になる原因

子どもがすきっ歯になる原因は、以下のとおりです。
乳歯と永久歯のサイズ差
基本的に、乳歯は永久歯より小さいです。そのため、永久歯が綺麗に並ぶためのスペースを考慮すると、乳歯列期にはある程度の隙間が必要と言えます。
顎の骨が成長したとしても、生えている歯の大きさが変わることはありません。乳歯列期に隙間があっても、顎の骨が適切に成長している証とも言えるので経過を観察することが多いでしょう。
上唇小帯に異常がある
上唇の内側から上の前歯の歯茎に伸びている筋を、上唇小帯といいます。これが通常よりも太かったり長かったりすると、前歯にすき間ができることがあります。
口周りによくない習慣がある
指しゃぶりや唇を噛む癖、舌で前歯を押す癖などは、歯に前方から継続的な力をかける原因になります。また、おしゃぶりやおもちゃを噛むことで、歯列や顎の発達に影響が出ることもあるでしょう。
このような癖があると、前歯が押し出されてすきっ歯になる可能性があります。
子どものすきっ歯をそのままにするリスク

上述した通り、すきっ歯は成長の過程で現れることも多いです。「そのうち自然になおる」と考える方も少なくないでしょう。
しかし、永久歯が生えそろった後もすきっ歯の場合、治療を検討すべきかもしれません。ここでは、子どものすきっ歯を放置することで起こり得るリスクについて詳しくみていきます。
見た目がコンプレックスになる
前歯は、口を開けたときに最も目立つ歯といえます。すきっ歯の状態だと、外見に対する意識が高まる年頃になるにつれて、本人がコンプレックスを抱く可能性があるでしょう。
特に、小学校中学年以降は、友人との会話や写真撮影などで歯の隙間が気になるようになり、自信を失う可能性も否定できません。
発音が不明瞭になる
歯と歯の間にすき間があると、舌が正しい位置に収まらず、空気が漏れて発音しにくくなることがあります。特に、サ行やタ行などは影響を受けやすく、発音が不明瞭になりやすいです。
幼少期の言語発達は、学習やコミュニケーションにとって非常に重要といえます。すきっ歯があることで正しい発音が習得できなかったり、口周りの筋肉の発達に影響を与えたりすることもあるでしょう。
虫歯や歯周病のリスクが高まる
歯と歯の間に隙間があると、汚れが詰まりやすくなります。そのため、細菌が繁殖しやすい環境といえるでしょう。特に、子どもの場合は、歯磨きが不十分になりやすいため注意が必要です。
また、歯と歯の間に汚れが残った状態が続くと、歯茎が炎症を起こして歯周病を発症するかもしれません。
噛み合わせが悪くなる
すきっ歯の場合、上下の歯列に均等に隙間があることは少ないです。そのため、上下の歯が正しく噛み合わなくなります。
噛み合わせが悪いために上下の歯の一部に負担がかかると、歯が欠けたり割れたりする可能性もあるでしょう。顎関節に過度な負担がかかり、顎関節症を引き起こす可能性もあります。
子どものすきっ歯はどうやって治療する?

ここでは、お子さまのすきっ歯の治療法を確認しましょう。
生活習慣の改善
すきっ歯が、指しゃぶりや舌癖、口呼吸などの癖によって引き起こされている場合には、その習慣を改善する必要があります。例えば、長期間にわたる指しゃぶりは前歯に持続的な圧力をかけ、すき間を拡大させる原因になります。
お子さまの場合、顎の骨の柔軟性が高いので、歯が移動しやすいです。癖によって隙間ができる可能性もありますが、癖をやめて歯にかかる不適切な力をなくせば、自然と隙間が埋まる可能性もあるでしょう。
矯正治療
永久歯へ生え変わったあとにすきっ歯が続いている場合には、矯正治療を検討します。永久歯列の治療には、ワイヤー矯正やマウスピース矯正が用いられることが多いです。
それぞれに異なる特徴があるので、お子さまの性格やライフスタイルに合った方法を選択しましょう。
上唇小帯の切除
上唇小帯の問題ですきっ歯になっている場合は、上唇小帯の切除を検討します。局部麻酔を使用して、患部を切除するのが一般的でしょう。
切除後2〜3日ほど痛みが出ますが、徐々に軽減します。痛みが悪化しないよう、食生活などに注意しながら様子を見てあげてください。
また、術後の細菌感染を防ぐために、抗生剤などが処方されることが一般的です。処方された薬をしっかり飲んで、安静に過ごすよう意識しましょう。
子どものすきっ歯を予防するためにできること

すきっ歯が気になっている方も多いかもしれませんが、すきっ歯が起こらないように事前に対策を講じておくことが大切です。すきっ歯は遺伝することもありますが、日常の生活習慣の影響を受けることもあります。
ここでは、子どものすきっ歯を予防するためにできることをご紹介します。
指しゃぶりなどの癖を早期に改善する
すきっ歯の原因となる指しゃぶりや、舌で前歯を押す癖などを早期に改善することが非常に重要です。小さな子どもは自分で癖を辞めることが難しく、習慣化すると歯並びに悪影響を及ぼす可能性が高くなります。
ただし、無理にやめさせるのは避けましょう。特に、指しゃぶりは2〜3ヶ月ごろから始まりますが、正常な発達の一環といえます。ある程度成長してからも、心を落ち着かせるために行っている子どもが少なくありません。
基本的に、指しゃぶりの癖は3歳頃までは行っていても問題ないとされています。それ以上続く場合は、少しずつやめられるように関わっていきましょう。
両手を使う遊びに誘うなど、自然に口元から手が離れるように促すのが理想です。
正しい姿勢を身につける
子どもの姿勢が悪いと、口が自然と開いて気づかないうちに口呼吸へとつながることがあります。特に、小さな子どもの場合、姿勢が悪いと身体の発育にも影響するため注意が必要です。
口呼吸が習慣化すると、口周りの筋肉のバランスが乱れるため歯並びが乱れる恐れがあります。
定期的に歯科検診を受ける
子どもの歯並びや噛み合わせは、成長とともに変化していきます。
しかし、1日で急激に変化するわけではないため、保護者が変化に気づくのは難しい場合もあります。歯科医院での定期検診を受けることで、歯の生え変わりや顎の成長を専門的にチェックでき、必要なタイミングでの対応が可能になるでしょう。
特に、乳歯から永久歯への生え変わり時期には、口内環境が大きく変わることでブラッシングなども難しくなります。適切にケアを行えるようにするためにも、定期検診を受けましょう。
まとめ

子どものすきっ歯は、乳歯の生え変わりや成長とともに自然に改善するケースも多いですが、永久歯の段階で残っている場合は治療を検討すべきでしょう。場合によっては、口元のコンプレックスや発音、虫歯などのリスクにつながることもあります。
すきっ歯の原因には、指しゃぶりや舌癖、上唇小帯の異常などさまざまなものがあります。お子さまの健康的な成長と自信のある笑顔を守るためにも、早めに歯科医院を受診して相談することが大切です。
子どものすきっ歯の治療を検討されている方は、兵庫県宝塚市「宝塚南口駅」より徒歩0分の宝南ショップス2階にある、宝塚南口駅の歯医者「宝塚歯科H&L」にお気軽にご相談ください。