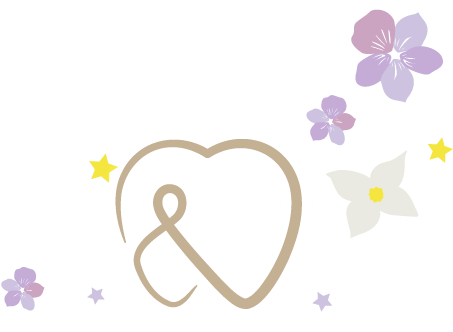こんにちは。兵庫県宝塚市「宝塚南口駅」より徒歩0分の宝南ショップス2階にある、宝塚南口駅の歯医者「宝塚歯科H&L」です。

虫歯治療を終えて銀歯を装着したからといって、安心してはいけません。実は、見た目ではわからない銀歯の下に虫歯が再発するケースは少なくありません。
このような虫歯は二次う蝕(にじうしょく)とも呼ばれ、初期段階では痛みなどの自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行することが大きな特徴です。治療済みの歯に再び虫歯ができるのはショックですが、原因を理解し、日々のケアを見直すことで予防可能です。
この記事では、銀歯の下に虫歯ができる原因から発見が遅れた場合のリスク、適切な治療法、そして再発を防ぐための予防策まで、わかりやすく解説していきます。すでに銀歯がある方、これから銀歯の治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
銀歯の下が虫歯になる主な原因

銀歯の下で虫歯が再発するのは珍しいことではなく、いくつかの明確な原因が存在します。以下で紹介する原因を知っておくことで、対策を立てやすくなります。虫歯を予防するためにも、銀歯の下が虫歯になりやすい理由を把握しておきましょう。
隙間から細菌が侵入するから
まず大きな要因となるのが、銀歯と歯の隙間からの細菌侵入です。銀歯は硬く丈夫ですが、天然の歯との接合部は時間とともに劣化することがあります。わずかな隙間ができると、その部分に細菌や食べかすが入り込み、虫歯が進行しやすくなります。
接着剤が劣化するから
次に考えられるのは、接着剤の劣化です。銀歯は専用の接着材で歯に固定されますが、この接着剤も長年使用しているうちに劣化し、密閉性が失われていきます。その結果、内部に唾液や細菌が入り込みやすくなり、再び虫歯が発生するリスクが高まるのです。
処置に不備があったから
治療時の処置の不備も、二次う蝕の原因になることがあります。初期治療の際に虫歯が完全に取り切れていなかった場合、銀歯の下で残った細菌が活動を続け、数年後に再発するケースもあります。
また、噛み合わせの力により銀歯がわずかにずれることで、知らないうちに隙間が生じる場合もあります。
日常のケアが不足しているから
最後に、日常のケア不足も大きなリスクです。銀歯の周辺はプラークがたまりやすいため、丁寧な歯磨きが不可欠です。デンタルフロスや歯間ブラシを使用しないと歯と銀歯の境目に磨き残しができやすく、そこから虫歯が広がることがあります。
銀歯の下の虫歯の発見が遅れるとどうなる?

銀歯の下にできた虫歯は、外から見えにくく痛みも出にくいため、気づかずに放置されやすいという特徴があります。
発見が遅れると、虫歯は静かに深く進行し、歯の内部組織や神経にまで達することがあります。こうなると通常の虫歯治療では済まず、根管治療と呼ばれる歯の神経を取り除く処置が必要になります。
さらに症状が進行すると、歯の根に膿がたまる歯根嚢胞や歯根破折といった重度のトラブルを引き起こすこともあります。これらの状態になると、歯の保存が難しくなり、最悪の場合には抜歯が必要になることもあるのです。
せっかく治療した歯を再び失うのは、患者さまにとって大きな損失と言えるでしょう。
また、虫歯が進行していることに気づかず、日常的に噛む力を加え続けると、銀歯そのものが外れる場合もあります。これによって歯の中がむき出しになり、一気に症状が悪化することもあるため注意が必要です。
こうしたリスクを避けるためには、定期的な歯科検診が欠かせません。レントゲンなどで内部の状態を確認することにより、早期発見・早期治療が可能になります。銀歯のある歯に痛みや違和感がなくても、油断せずに定期的に診てもらうことが大切です。
銀歯の下の虫歯を治療する方法

銀歯の下に虫歯が発見された場合、まず行われるのが銀歯の除去です。見えない部分に虫歯がある以上、銀歯を一度取り外さなければ正確な診断も治療もできません。銀歯を除去した後、虫歯の進行度合いに応じて、適切な治療法が選択されます。
虫歯が浅い場合は、感染した部分を削り、新たな詰め物や被せ物をするだけで済むこともあります。
しかし、虫歯が神経に達していた場合には根管治療が必要になります。根管治療では、歯の内部の神経や細菌を取り除き、内部をきれいに洗浄・消毒してから充填材で密閉します。この処置には数回の通院が必要で、再発防止のためには非常に重要な工程です。
治療後は再び被せ物を装着しますが、近年では銀歯に代わってセラミックなど、より精密にフィットしやすく、見た目も自然な素材を選ぶ方が増えています。これらの素材は金属アレルギーの心配もなく、歯と接する面の密閉性が高いため、再発リスクも抑えられるのが特徴です。
また、治療の際にはマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を活用する歯科医院も増えており、細かい部分まで確認しながら処置することで、より確実な治療が可能となります。
いずれにしても、虫歯の再発を防ぐには治療の精度が重要です。安易に銀歯を取り替えるのではなく、しっかりとした診断と適切な治療方針を持つ歯科医院を選ぶことが大切です。
銀歯の下が虫歯になるのを防ぐには

銀歯の下に再び虫歯をつくらないためには、日常のケアと定期的な検診の両方が欠かせません。ここでは、銀歯の下が虫歯になるのを防ぐためにできることをいくつか紹介していきます。
丁寧な歯磨き
まず基本となるのは、丁寧な歯磨きです。特に、銀歯の縁は汚れがたまりやすく、虫歯の原因菌が繁殖しやすい部分です。歯ブラシだけではなく、デンタルフロスや歯間ブラシを併用して、隙間に残ったプラークをしっかり取り除くことが大切です。
フッ素入り歯磨きの使用
また、フッ素入り歯磨き粉の使用も効果的です。フッ素には歯の再石灰化を促し、初期の虫歯の進行を抑える働きがあります。銀歯の周辺の健康な歯質を守るために、毎日のケアに取り入れましょう。
食生活の見直し
加えて、食生活も見直すべきポイントです。糖分の多い飲食物を頻繁に摂ると、口内の細菌が活性化しやすくなります。甘いものを食べた後は水で口をすすぐ、間食を控える、よく噛んで唾液を分泌させるといった工夫が、虫歯予防に役立ちます。
銀歯の寿命と再装着のタイミングを知る
銀歯にも寿命があり、永久に使えるものではありません。一般的に銀歯の耐用年数は5〜10年とされており、使用年数が経過すると接着剤の劣化や歯との隙間の発生が起こりやすくなります。これを放置すると、隙間から細菌が入り込み、虫歯が再発するリスクが高まります。
見た目に問題がなくても、内部で劣化が進んでいる可能性があるため、年数に応じて歯科医院でのチェックを受け、必要に応じて再装着や交換を行うことが重要です。自覚症状が出る前に対処することが、歯を守るうえで何よりも大切です。
銀歯以外の選択肢を検討してみる
虫歯治療の被せ物として広く使われている銀歯ですが、現在では審美性や耐久性に優れた代替素材も多く登場しています。セラミックやジルコニアなどは、歯との密着性が高く、隙間の発生を抑えることができるため、虫歯の再発リスクを軽減できます。
また、金属アレルギーの心配もなく、自然な色合いで見た目も美しく保てるのが特徴です。費用は銀歯より高くなる傾向がありますが、長期的に見れば再治療の手間や費用を抑えられる可能性もあります。
定期的な歯科検診
最も重要なのが、定期的な歯科検診です。目に見えない銀歯の下の虫歯は、自分では気づくことができません。3〜6か月に1回程度のペースで歯科医院を受診し、レントゲンや歯科医師によるチェックを受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。
もし銀歯が古くなっている場合は、歯科医師と相談の上で再装着や素材の変更を検討することも有効です。最新のセラミック素材などは、歯と密着性が高く、再発リスクを下げる点でも注目されています。
まとめ

銀歯の下にできる虫歯は、外からは見えず、痛みも出にくいため発見が遅れがちです。
しかし、放置していると深刻な状態に進行し、最悪の場合は歯を失うことにもつながります。主な原因としては、銀歯と歯の隙間からの細菌侵入や接着剤の劣化、日常のケア不足などが挙げられますが、これらは意識と対策によって十分に防げるものです。
日々の丁寧な歯磨き、デンタルフロスの使用、食生活の見直し、そして何より定期的な歯科検診を欠かさないことが、銀歯の下の虫歯を予防する最善の方法です。また、すでに銀歯が古くなっている場合には、素材や接着方法を見直すことで、再発リスクを低減できます。
治療した歯を長く健康に保つためにも、一度治療が終わったからといって安心せず、日常的なケアと専門的なチェックを継続していくことが重要です。
銀歯の下の虫歯の治療を検討されている方は、兵庫県宝塚市「宝塚南口駅」より徒歩0分の宝南ショップス2階にある、宝塚南口駅の歯医者「宝塚歯科H&L」にお気軽にご相談ください。